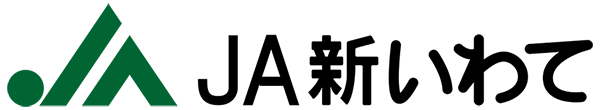農のかたち〜私流〜
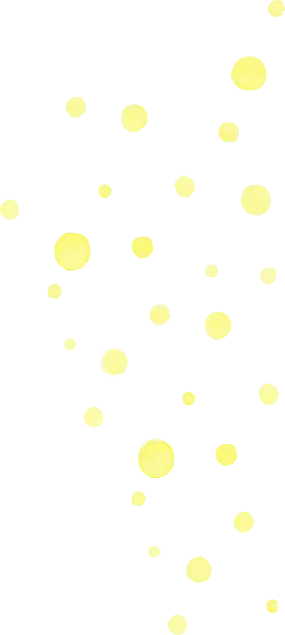
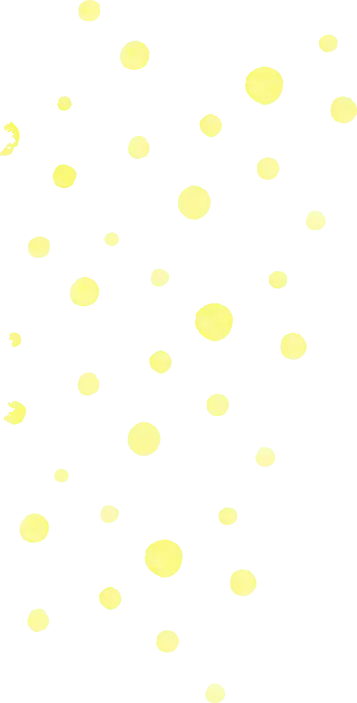
一人じゃない 多くの支えに感謝

雫石町でリンドウ38aとハウス3棟で切り花を生産する梨良さん。34歳の時に生まれ育った東京から夫の実家がある雫石町に移住。当初は絶対に農業はやらないと断言していたが、ふと見かけた田園の中に咲くリンドウの姿に感動を覚えた。今では多くの人の支えによって、花農家として歩みを進めている。
やらないと決めた農業
東京で生まれ育った梨良さんは夫の俊一さんと東京で暮らしていた。雫石町にある夫の実家には何度か足を運び「いつかは、ここで暮らしてほしい」と言われていたので、老後はここで暮らすのだろうと漠然と考えていた。しかし、夫の父が亡くなり実家の田んぼの作業ができる人がいないことで、34歳の時に移住することになった。梨良さんは地元の人たちには「絶対に農業はやらない」と宣言して、雫石町へ移り住んだ。

夫の実家の目の前には、広大な田畑が広がっていた。まわりの助けを借りながら夫が田んぼの作業をしていた。そんな姿を見ていた梨良さんは「機械にも乗れないし自分にはできない。これからどうなるんだろう」と考えていた。
そんな頃、車を走らせていると田んぼの中に咲いている花を目にした。「自分の背丈くらいまで真っすぐ伸びて咲いている姿に感動した」と、その時の情景を思い返す。その花が気になった梨良さんは親戚の花農家に聞き、リンドウという花だと知った。そして「一緒にやらない?」と切り出された。

そんな話がJAの担当者にも伝わり、リンドウ畑を見せてもらったり、花の女性生産者グループの活動に参加するようになっていた。次第にメンバーの明るさに引き込まれていき、農業は汚い、辛いというイメージから、楽しそうという気持ちに変わっていった。そして「大丈夫、できるから!」と言う一言が背中を押し、就農を目指す決意をした。
農業は一人じゃない
就農に向けて農業大学校に通いながら、花農家での研修を始めた。農業大学校では農業を基礎から学び、研修先の農家では、一つ一つの作業の目的や理由を教えてもらい、花づくりの基本を身に付けていった。そして、令和6年4月に夫と一緒に就農した。

2年間の研修で基本は学んだものの、すべてがうまくいく訳ではなかった。ある日、一人で畑に防草シートを張っていて風で飛ばされそうになったが、偶然通りすがったリンドウ農家の仲間が手伝ってくれた。「『今日やらなきゃないんでしょ?』と言って、全て張り終えるまで一緒に作業をしてくれた。この時は、本当に一人じゃないんだと実感した」と話す。そして、「就農に至った今の自分があるのは、JAの担当者がリンドウ栽培を始めやすい環境を作ってくれたことが大きい。マルチ張りも部会の人に張ってもらえて助かっている」と笑顔で話す。
「まわりがいるから自分でもできる」と話す梨良さん。JAの担当者の熱意や、その気持ちを理解する多くの農家がいることが、農業をやらないと決めていた梨良さんの心を動かしたのだ。また「作った花を贈った人が笑顔になり、困った時に力を貸してくれる人がいる環境が、農業へのイメージを大きく変えた。今はやりがいを感じている」と話す。今後は「リンドウ栽培の事を広めていき、パートでも就農でも花の生産に携わる人を増やしていきたい。そして、子どもたちが自慢できるような農家を目指したい」と笑顔で話す。始めは引きずり込まれたという気持ちもあったが、今は「感謝」という気持ちに変わっている。

JAと南部地域花卉生産部会で新規でも始めやすいよう取り組みを進め、年に一度しか使わないマルチ張りは部会で請け負う体制が整っています。また、まわりの生産者を助け合う環境も浸透し、定植なども助け合いながら作業を行っています。
プロフィール

細川 梨良 さん
雫石町に来てから車の免許を取り、ドライブで県内の全市町村制覇を目指しています。
※広報誌「夢郷」 2025年8月号掲載時の情報です。掲載情報が変更となっている場合がございます。
このページはお役に立ちましたか?