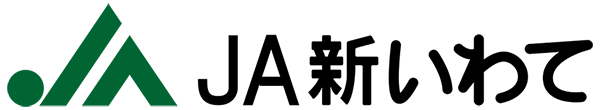農のかたち〜私流〜
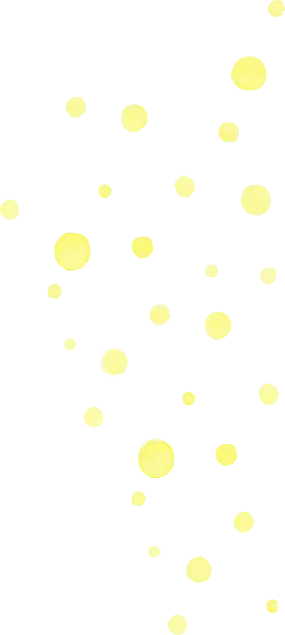
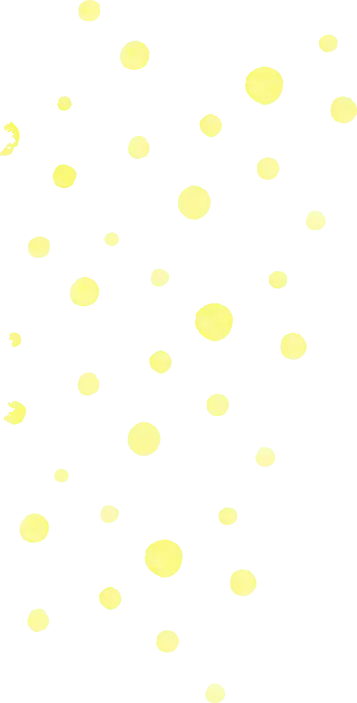
野菜作りを 地域の産業に

岩泉町で水稲50aとブロッコリー40a、キュウリ6aなどの野菜を作付けする慎也さんは就農から3年目を迎える。先に就農した仲間たちの成長に焦りを感じた時もあったが、今は支え合える仲間として共に歩んでいる。野菜作りが地域の産業として認められる日を夢見ている。
生まれた土地で生きていく
実家は水稲農家で一人っ子として育った慎也さん。小さい頃からいろんなことに興味を持ち「鉄道が好きで、将来は鉄道に関わる仕事も考えたことがあった」と話す。しかし、いずれは実家を継がなくてはという気持ちも心の中にあった。実家では昔から米を作っていたが、小学4年生の時に父親がビニールハウスを建てて野菜を作り始めた。

「様々な野菜を作り、その野菜が食卓に並ぶことに幸せを感じた」と当時を話す。新鮮な野菜のおいしさにも喜びを感じ、作業をよく手伝うようになっていた。
好奇心旺盛な慎也さんだったが、実家を継ぐという中で「農業」という選択肢を考えるようになっていた。弘前大学に進学した慎也さんは農村整備や都市と農村の交流などを学んだ。「多くの農家の姿を見たことは、就農した今では参考になることも多い」と話す。卒業後は、県内の農業法人に就職。地元での就農に向けて実践を通し米作りを経験した。

就職して数年経った頃、友人から早く地元に戻ってくるように話をされた。いずれはと考えていた慎也さんは、一つのタイミングだと考え、地元に戻り岩泉農業振興公社で働き始めた。堆肥センターや採草部門を担当していたが、知り合いの農家が楽しそうに野菜を作り、成長していく姿を見ているうちに焦りを感じるようになっていた。
「今の仕事は自分がやりたいことと違うのでは?」と感じた慎也さんは、7年勤めた公社を退職し令和5年に就農した。「平成28年の台風10号で農地が被害を受けたこともあり就農のタイミングは遅くなった」と話す。まわりの農家からの遅れを感じながらの就農となった。
身近に感じられる仲間
地元に戻った時、JA青年部や4Hクラブに入っていた慎也さんは、野菜農家との交流もあった。就農1年目はブロッコリーとキュウリを生産する農家を手伝いながら栽培技術を学んだ。「米だけでは厳しいので野菜との組み合わせを考えていた。地域で生産される品目であれば学ぶ機会があるので、ブロッコリーとキュウリを中心とした作型にした」と話す。

しかし、1年目の秋に収穫を予定していたニンジンが8月の集中豪雨ですべて流された。「その時は、かなりショックを受けた。まわりから遅いと言われたが種をまき直してみた。収穫時期は遅くなったが甘くておいしいニンジンを収穫することができた」と笑顔で話す。農業の大変さとおもしろさを感じる経験となった。
2年目にはブロッコリーとキュウリを自ら作付けした。「この地域は、分からないことは教え合い、行けば圃場を見せてくれる農家が多い。それぞれの農家まで距離はあるが、存在はすごく近く感じる」と語る。そして、就農2年目には収穫した野菜が食卓に並び、子どもの頃を思い返した。
焦りを感じてのスタートも、まわりの協力を得ながら成長することで自信へと変わり始めている。そして「町内に野菜農家はまだ少ないが、地域の産業として評価されるような経営を目指していきたい」と語る。その原動力の源には、子どもの頃に見た幸せな食卓を多くの人にも感じてもらいたいという気持ちがあるのだろう。

新鮮でおいしい野菜を地元の皆さんにも食べてもらうため、自宅の前に直売所を設置し、地産地消にも取り組んでいます。今年は新たにスイートコーンを作付けしました。今後も地域の気候に合った野菜の栽培にも挑戦していきます。
プロフィール

千葉 慎也 さん
子どもの育児もあり忙しい日が続きますが、ゆっくり温泉旅行にもいきたいですね。
※広報誌「夢郷」 2025年7月号掲載時の情報です。掲載情報が変更となっている場合がございます。
このページはお役に立ちましたか?